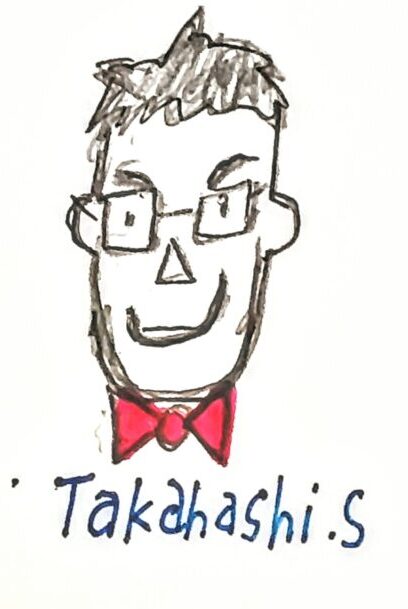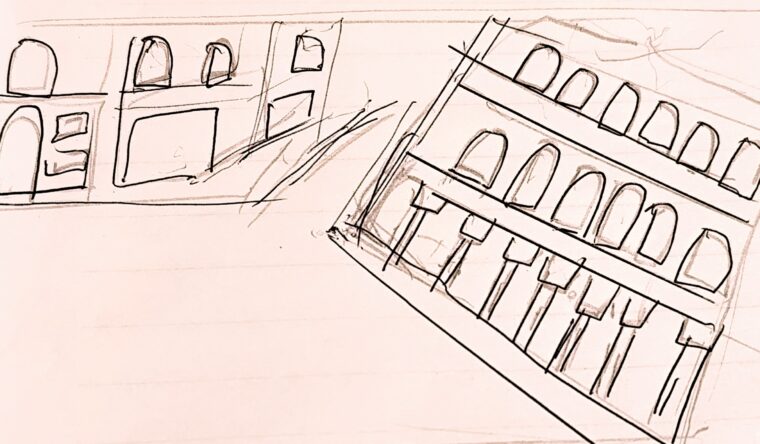2010年代から話題となった『同調圧力』。今でも、「どのようにしたら相手が嫌がるのか」「自分がされて嫌だったことは何か」が問題視されています。
一言で言うと『相手によって大きく変わること』だと思います。同調圧力は嫌です。
そこで今回は、共感できるエピソードを交えながら説明します。
自分がやる人の嫌がることは ?
このブロガーは、無意識にやってしまう『人が嫌がること』は以下のように分析します。
・感情的に爆発すること
理不尽なルールや態度に対して、「怒って切り捨てよう」とする姿勢は、相手にとって攻撃的に映る可能性があります。特に「キレた」「食って掛かる」という感情的な反応が相手を不快にさせることがあります。
・ルールや慣習を否定すること
「謎ルール」に対して「意味はない」断言し、ガツンと言う姿勢は、保守的な人やそのルールに価値を感じている人にとっては、挑発的に感じられるかもしれません。
・自分の合理性を他人に押し付けること
「合理的に生きていこう」と繰り返す一方で、他の人の価値観や背景を理解しようとする姿勢が弱く、結果として自分の正しさを強く主張してしまう傾向があります。
自分がされて嫌だったことは ?
自分がされて嫌だったことは、以下の通りです。
・理不尽なルールの押し付け

押し付けたルールが気に入らなかった
と言っており、納得できないルールに従わされることに強い不快感を抱いています。
・因縁つけられること
「なんでできないの ! 」と因縁つけられてつまらない思いにつながり、ケンカに発展してしまいます。
・閉じたコミュニティでの忖度や同調圧力
「村八分になることが恐ろしい」
「忖度して礼儀作法を守る」
といった同調圧力や忖度の文化に対するに対する嫌悪感が読み取れます。
このブロガーの人間関係の傾向
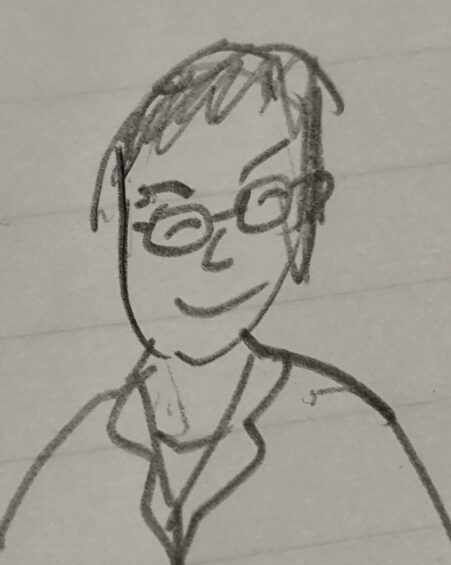
合理性を重視するが、感情的に爆発もあります。理屈に合わないことを強く反発する一方で、感情的な反応も見られます。これは合理性や感情の間で葛藤している証拠です。
意味ないものをつぶしていくことが社会の改善につながります。対立を避けるより、声を上げて変えていくことを重視しています。つまり、対立を恐れず、改善を志す姿勢が大事です。
「村八分が恐ろしい」としながらも、ガツンと言う姿勢は、孤立への恐怖を乗り越えようとする強さを感じます。
知り合いの重要性
ある食品メーカーのスタッフの気持ちを正確に予測できるのであろうか ? それとも、そのほかの群衆の知恵なのか ? 問いに対する答えが後者だった人は、大規模なネットワークの力を理解しています。グローバル化の進展に伴い、この種のネットワークの重要性は高まります。先生、親、大学教授、家族、先輩、上司、友達、部下、仲のいい同僚、特に親しい人たちー「絆」を通じて、就職に有利だろうと思っていました。しかし、実際は親しい友人よりただの知り合いから相手の気持ちを読み取れるケースがあります。